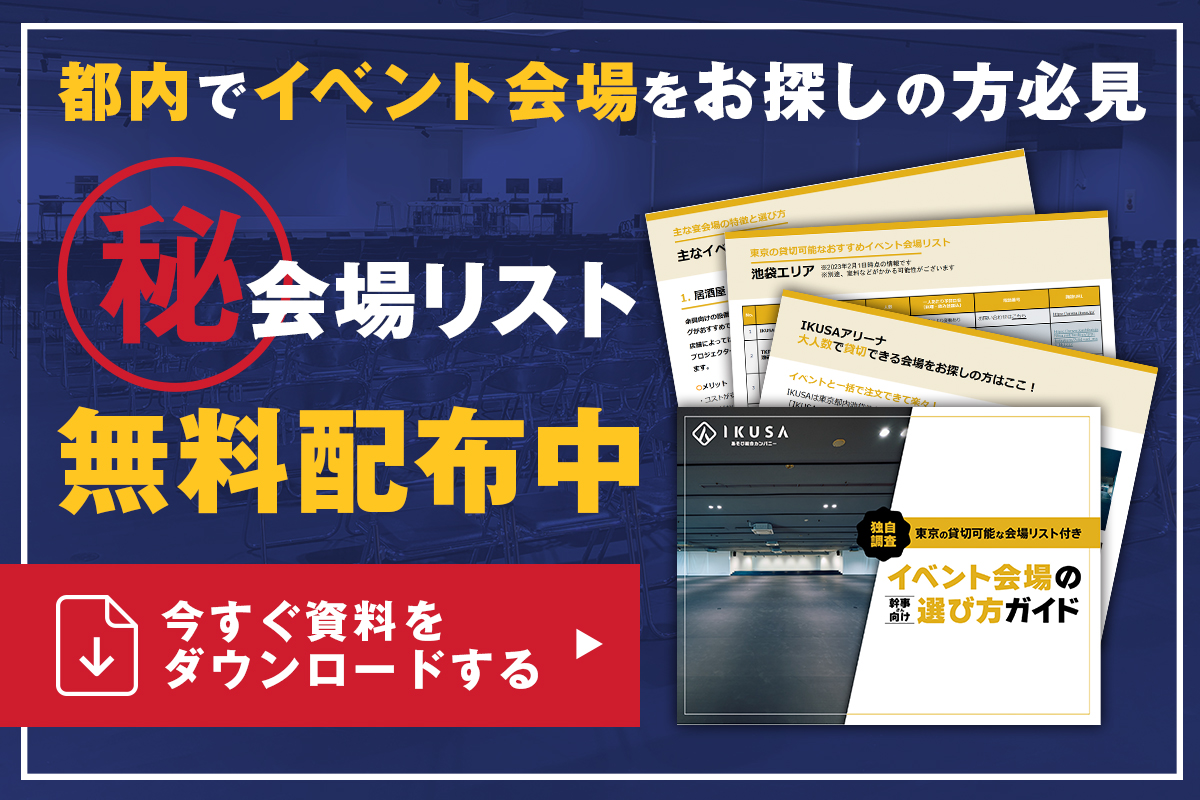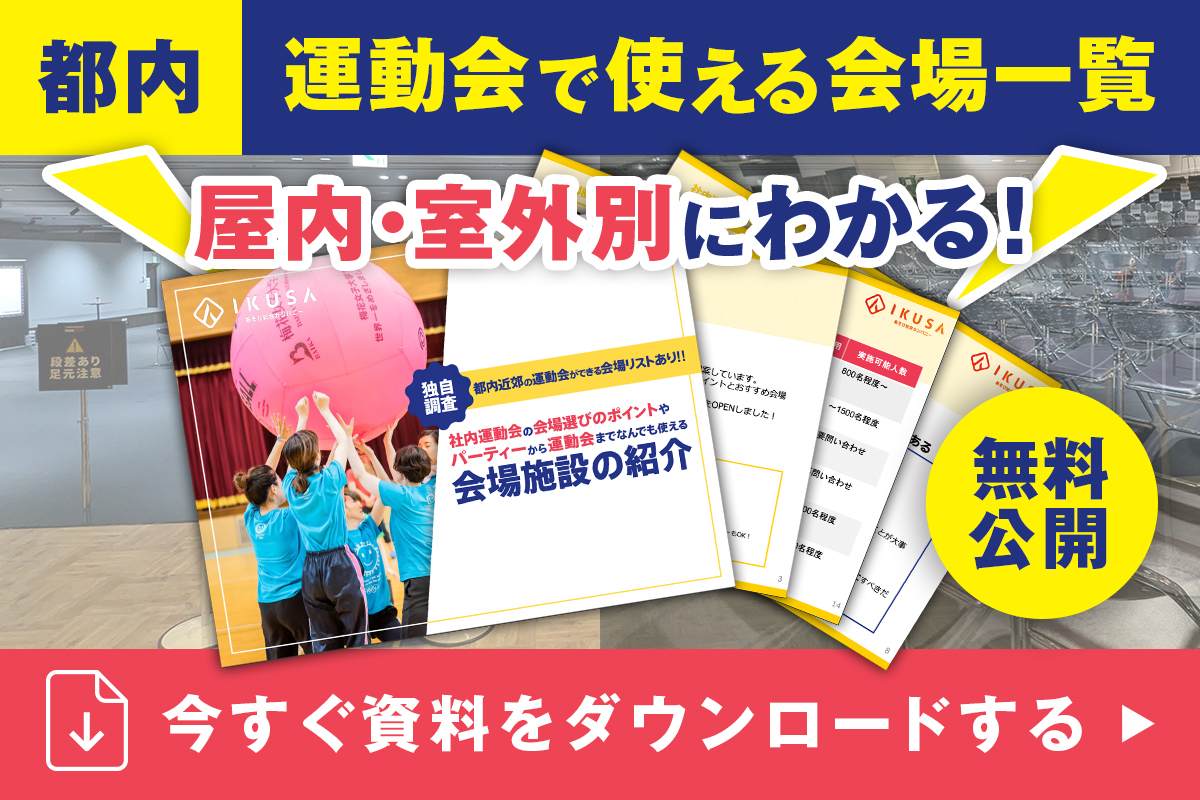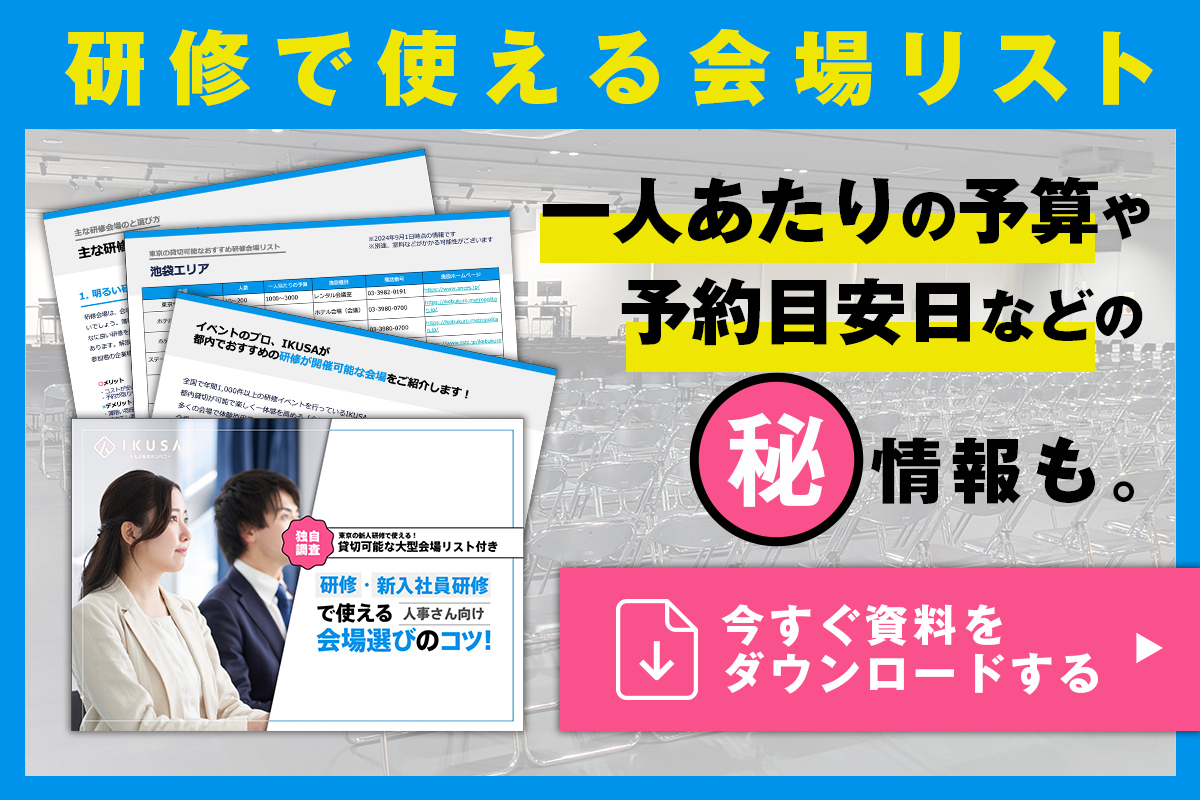展示会の企画16選!展示会の種類や出展までの準備、企画例を紹介

目次
展示会とは、特定のテーマに沿った製品やサービスを取り扱う企業・団体が自社ブースを出展し、来場者との直接的なコミュニケーションを通じて新規顧客や見込み客を獲得する販促イベントです。多くの来場者を集める展示会では、ブース企画や演出に工夫を凝らすことで他社との差別化を図り、ブランド認知や販路拡大につなげられます。
本記事では、展示会の基本的な概念や種類、そして出展前からイベント終了後までの実施方法をわかりやすく解説するとともに、企画アイデア16選も紹介します。
大人数のレクリエーションにぴったりの会場をお探しですか?都内有数の広さと充実した設備を持つ「IKUSA ARENA」なら、企画・運営まで一貫してサポートできます。
展示会とは

展示会は、製品やサービスを実際に体験できる場であり、直接のアプローチが可能なため、消費者やビジネスパートナーとの信頼関係を構築しやすいのが特徴です。具体的な目的としては、以下のようなものがあります。
- 新規顧客獲得・リード獲得
- 販売促進・販路拡大
- ブランド認知向上・業界ネットワーキング
来場者がすでにテーマに興味を持っているため、効率的にターゲットにアプローチできます。また、その場での試食や試着、実演などにより、商品やサービスの魅力を直接訴求できるのも魅力です。ブース運営を通じたコミュニケーションで、企業のブランド価値や業界内での信頼性を高める効果も期待できます。
展示会の種類
展示会は、目的や対象となる来場者、規模によって主に以下の5種類に分類されます。
種類 | 特徴 | 主な目的 | 主な来場者 |
合同展示会 | 複数の企業・団体が一堂に会して展示を行う |
|
|
展示即売会 | ファッションやグルメなど、実際に試着・試食できる |
|
|
プライベートショー | グループ企業を含む一企業のみで開催する |
|
|
パブリックショー | 特定のテーマやジャンルの商品を展示し、来場者にアピールする |
|
|
オンライン展示会 | オンライン上で開催される展示会 |
|
|
近年では、対面とオンライン両方の形式を組み合わせた、ハイブリッド展示会も増加傾向にあります。
展示会の実施方法

展示会の実施方法を解説します。
出展目的の明確化
展示会に出展する前に、まずは自社の目的をはっきりと定めましょう。例えば、「販路拡大」や「ブランド認知の向上」「新規顧客獲得」など、目的に応じてターゲットや企画内容が変わります。目的を明確にすることで、最適なターゲット選定や目標設定、企画内容の考案につながり、出展後の評価もしやすくなります。
ターゲット・出展目標・予算の決定
展示会のターゲットを明確にし、「どのようなターゲットに向けた展示なのか」「商品を販売する場合には、どの程度の販売金額を見込むのか」などを具体的に決定しましょう。目標は、「来場者数〇人以上」や「売上〇円達成」など、具体的な数値で設定します。
展示会への出展には費用がかかるため、スタッフの人件費やブースの制作費を含めても黒字になるような目標を立てましょう。
また、BtoBとBtoCのどちらをターゲットにするかによって、目標設定の考え方が異なります。
- BtoB: 商品の販売数や来場者数に加えて、リード獲得数(見込み客数)の目標を設定するケースもある
- BtoC: 商品の販売数や売上金額など、販売活動が重視される
出展する展示会の選定と出展商品の決定
ターゲット層や目的に合わせ、出展する展示会の種類を選びます。また、イベントで売り込む商品やサービスは、今最もアピールしたいものや新商品を中心に選ぶと効果的です。
ブースのコンセプトや企画の立案
展示会における成功のカギを握るのが、「ブースのコンセプト設計」と「事前の集客活動」です。
まず、ブースのコンセプト立案では、自社の製品やサービスの強みが来場者に明確に伝わるよう、ブース全体の世界観を構築しましょう。例えば、製品の特徴やブランドイメージに合わせて配色を工夫したり、視覚的にインパクトのあるレイアウトにすることで、遠くからでも目を引くブース作りが可能です。
また、ただ展示するだけでなく、「体験」を通じて来場者に印象づける企画を盛り込むことも検討しましょう。具体的には、食品であれば試食、アパレルであれば試着といった体験型企画や、スタッフによる実演販売、製品説明のデモンストレーションなどが挙げられます。
さらに、来場者の記憶に残るキャッチコピーやインパクトのある装飾を施すことで、他社ブースとの差別化を図れます。
制作物やノベルティの作成
パンフレットや会社案内、商品カタログはもちろん、記念品やノベルティなども事前に用意します。発注スケジュールには十分な余裕を持たせましょう。特にノベルティは、ブースへの誘引効果が高く、来場者に自社名を覚えてもらうきっかけにもなります。ノベルティには企業ロゴやブランドカラーを取り入れることで、販促ツールとしての効果をさらに高めることも可能です。
集客・告知・宣伝活動
自社ホームページやSNS、メールマガジンなど、複数のチャネルを活用して情報を発信しましょう。展示会の開催日時や場所、出展内容だけでなく、「当日ブースで何が体験できるのか」「どんなノベルティがもらえるのか」といった魅力的な情報を添えることで、来場者の期待感を高められます。また、展示会情報を掲載するイベント専門サイトに登録することで、展示会を探している新規ユーザーへの認知拡大も可能です。
スタッフのシフト調整や運営計画の策定
各スタッフの担当業務や役割を事前に明確にし、混乱を避けるための詳細なスケジュール表を作成します。展示会では、来場者への案内や商品の説明、ブース内の機材管理、さらには緊急時の対応など、多岐にわたる業務が発生するため、誰がどのタイミングでどの業務を担当するのかを具体的に決めておきましょう。
また、シフト調整だけでなく、当日の運営計画も重要です。運営計画には、展示会の開始から終了までのタイムラインを含むとともに、ブース設営や機材搬入、休憩時間、交代要員の配置、さらにはトラブル発生時の連絡体制や代替措置など、予期せぬ事態への対策も盛り込む必要があります。各部署やスタッフ間で情報共有を徹底し、役割分担を明確にすることで、柔軟に対応できる体制を整えましょう。
イベント当日の運営
スケジュールに沿ってブース運営を行います。企画段階で設定した目標をもとに、来場者の対応や販促、声掛けなどを行いましょう。接客の中でリード獲得が可能と判断したら、実際に商品を体験してもらったり相手の情報を得て、イベント後のアプローチにつなげます。
展示会の最中は、目標の数字と実際のリード獲得数を適宜照らし合わせながら、展示会の終了まで来場者への声掛け対応などを継続しましょう。
イベント後のフォロー
展示会終了後は、入手した名刺や情報を基に、見込み客リストを整理して、フォローアップを実施します。以下の方法が効果的です。
- 商品やサービスの詳細情報を送付
- 次回イベントの案内や割引クーポンの提供
- アンケート調査によるフィードバックの収集
展示会では多くの見込み顧客を発掘できますが、獲得したリストを有効活用できなければ、最終的な利益には直結しません。展示会を有効活用するためにも、見込み顧客のアフターフォローに力を入れましょう。
体験型・実演型の展示会企画例5選

まずは、体験型・実演型の企画例5選を紹介します。
試食・試着・試飲などの体験ブース
来場者が実際に商品を試せる体験型ブースは、展示会の定番人気企画です。試食や試着・試用などを通して商品の魅力を直感的に伝えられて記憶に残りやすく、購買意欲の向上にも効果的です。リアルな使用感を体感してもらうことで、自社の信頼性アップにもつながります。
体験ブースでは、商品の「強み」が伝わる内容にすることが大切です。食品なら味や香り、機械なら操作性など、最も訴求したい部分を体感させましょう。試食・試用には衛生管理や同意取得が必要な場合があります。準備や動線設計も忘れずに行いましょう。
ワークショップ・セミナー
ブース内で開催されるワークショップやセミナーは、自社の専門知識や製品の特徴を深く伝える絶好の機会です。最新トレンドや業界動向を絡めた内容なら参加者の関心も引きやすく、企業のブランディング強化にもつながります。
ターゲットの関心に沿ったテーマを設定し、短時間で価値ある情報を提供できる構成にしましょう。時間帯によって参加者数にバラつきが出るため、複数回実施したり、事前予約制にしたりする工夫も有効です。
ものづくり体験
来場者自身がオリジナルアイテムを制作できる「ものづくり体験」は、展示会ならではの没入型コンテンツです。制作したアイテムを持ち帰れるため、帰宅後も自社への関心が継続しやすく、企業イメージの定着に効果があります。
体験を通じて、ブランドや商品の世界観を伝えるように設計するのがポイントです。参加人数の制限や所要時間をあらかじめ明示し、混雑を避ける配慮も行いましょう。
パフォーマンス・実演形式
目の前で製品の性能や使い方を見せる「実演ブース」は、視覚と聴覚を使って商品の価値を直感的に伝えられるのが魅力です。疑問点をその場で解消できるため、成約率アップにもつながります。
時間を決めてスケジュール制にすると、人だかりができやすく、注目度がアップします。スタッフのスキルやトーク内容にばらつきが出ないよう、事前に台本を作成したり練習をしたりしましょう。
サンプル・ノベルティの配布
来場者への無料配布は、展示ブースへの誘導施策として有効です。特に自宅に持ち帰れるグッズや試供品は、自社ブランドの認知度拡大や話題作りにもなります。ターゲットに合わせたアイテム選びが成功の鍵です。
商品理解が深まる説明資料とセットで渡すとより効果的です。ノベルティは実用性・話題性の高いものを選びましょう。配布数や対象を限定しない場合、早期に在庫切れする恐れもあります。計画的な運用を行いましょう。
デジタル技術を活用した展示会企画4選

続いて紹介するのは、デジタル技術を活用した企画例です。
動画や音声を使った製品紹介
動画や音声を用いた製品説明は、スタッフの負担を減らしながら、効率よく製品の魅力を伝えられます。接客の隙間時間でも来場者の関心を引けるため、ブースの稼働率向上にもつながります。
テキストよりも「感情に訴える映像」や「分かりやすいナレーション」を心がけましょう。音量や映像の明るさが他ブースに影響しないよう、機材の配置や環境調整が必要です。
AR・VR技術を使った体験
製品の使用シーンや仕組みを仮想空間で再現できるAR・VRコンテンツは、実物が用意できない場合にも活躍する企画です。臨場感あるデモンストレーションで、来場者に強烈な印象を残せます。
実製品では伝えきれない使用シーンを再現し、来場者の想像力を刺激しましょう。酔いやすさや操作の難しさに配慮し、操作補助スタッフを配置すると安心です。
3Dファントム(ホログラムサイネージ)
LEDを使った3Dファントム映像は、肉眼で楽しめる立体的なホログラムとして注目を集められる企画です。非日常的な視覚体験でブースの話題性を高め、SNSでの拡散も期待できます。
製品の動きや分解図を立体的に見せると、理解促進や視覚的インパクトが増します。暗めの照明が必要な場合があるため、ブースの構造や照明設計も工夫しましょう。
タッチパネル型デジタルサイネージ
来場者が自ら操作できるデジタルサイネージは、興味関心に応じた情報提供が可能です。ストレスのない情報取得体験は、ブランドへの好印象や信頼感の向上にもつながります。
来場者が自分のペースで情報収集できる設計が理想です。選択肢や導線をシンプルにしましょう。また、機器のメンテナンスやトラブル時の対応方法を事前に決めておくことも大切です。
話題性と集客力アップにつながる展示会企画4選

展示ブースへの集客や話題性のアップを重視した企画を紹介します。
フォトスポットの設置
SNS映えを狙ったフォトスポットは、集客効果抜群の企画です。おしゃれな空間演出やトリックアートなど、撮影意欲をかき立てる仕掛けを設置すれば、SNSでのシェア拡散による認知拡大にもつながります。
ハッシュタグやブランドロゴを背景にさりげなく入れると、拡散時の宣伝効果もあります。撮影待ちが発生する可能性があるため、列の整理や混雑対策が必要です。
スタンプラリー
複数のブースを回遊させるスタンプラリーは、展示会全体の盛り上げ施策として効果的です。参加者に景品を用意すれば、リード獲得にもつながります。
複数ブースを回る仕組みを作ることで、展示会全体の回遊率向上にもなります。台紙や景品の在庫管理、スタンプの設置場所の案内など、運営面の工夫を行いましょう。
リアルタイムでのプロモーション活動
トークイベントや製品紹介をInstagramやTikTok、YouTubeなどのライブで届けると、現地にいない層にも訴求できます。配信中の音声トラブルやネット回線の不安定さに備えて、事前のテストをしっかり行いましょう。
カプセルトイ
来場者が参加できるカプセルトイ企画は、体験型のエンタメ要素として人気です。QRコード連携で顧客情報を収集できる仕組みにすれば、マーケティング活用にもつなげられます。混雑しやすいため、整理券制や誘導スタッフの配置でスムーズな進行を心がけましょう。
デザインと演出にこだわった展示会企画3選

最後に紹介するのは、出展ブースの演出やデザインを重視した企画です。
テーマカラーを統一したブース設計
商品やサービスのイメージに合わせてテーマカラーを設定すると、統一感のある魅力的な展示空間が完成します。統一感のあるブースは視覚的に印象に残りやすく、他ブースとの差別化にもつながります。
自社ブランドカラーと統一し、ロゴやサイン・什器まで一貫性を持たせて認知向上を狙いましょう。しかし、色使いが偏りすぎると視認性が下がることもあります。補色の活用でバランスを取るのがおすすめです。
ブランドストーリーテリングの活用
企業や商品の歩みを物語形式で紹介することで、来場者の共感を呼ぶストーリーブースが完成します。情緒的な訴求で商品の背景にある価値まで伝えましょう。
ストーリーの中に「課題→解決→成果」といった構成を入れると共感が生まれやすくなります。長文になりすぎず、ビジュアルや短いコピーで伝える工夫が必要です。
漫画風パネルの展示
文字よりも直感的に伝えられる「漫画パネル」は、視覚的訴求力の高い展示手法です。ストーリー仕立てにすることで、製品の魅力やメッセージがより深く伝わります。
ユーモアや親しみやすさを出すことで、硬いイメージの製品も柔らかく紹介できます。専門的すぎる内容を漫画化すると逆に分かりづらくなることがあるため、構成は慎重に作成しましょう。
まとめ

展示会は、来場者と直接コミュニケーションを取れる貴重な機会です。例えば、「その場で自社製品を体験してもらう」「実演を通じて具体的な利用シーンをイメージしてもらう」といった工夫により、製品の魅力をしっかり伝えられます。また、来場者の目を引くパネルや、思わず足を止めたくなるユニークな企画を用意すれば、自社ブースへの集客効果が高まり、結果として多くの見込み客を獲得するチャンスにもつながります。
都内でイベント会場をお探しなら、700人まで収容可能なIKUSA ARENAがおすすめです。
スポーツイベントから懇親会まで、幅広い用途に対応できる会場の空き状況と料金プランを今すぐチェックしませんか?