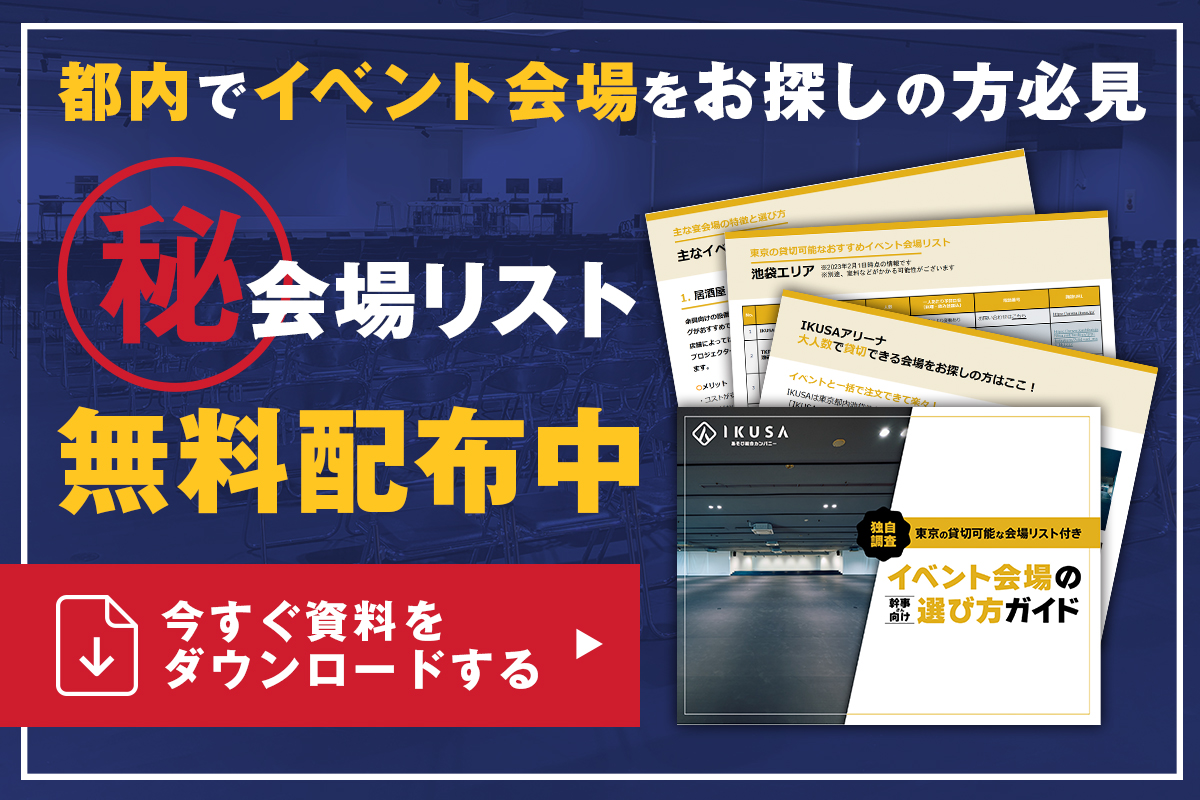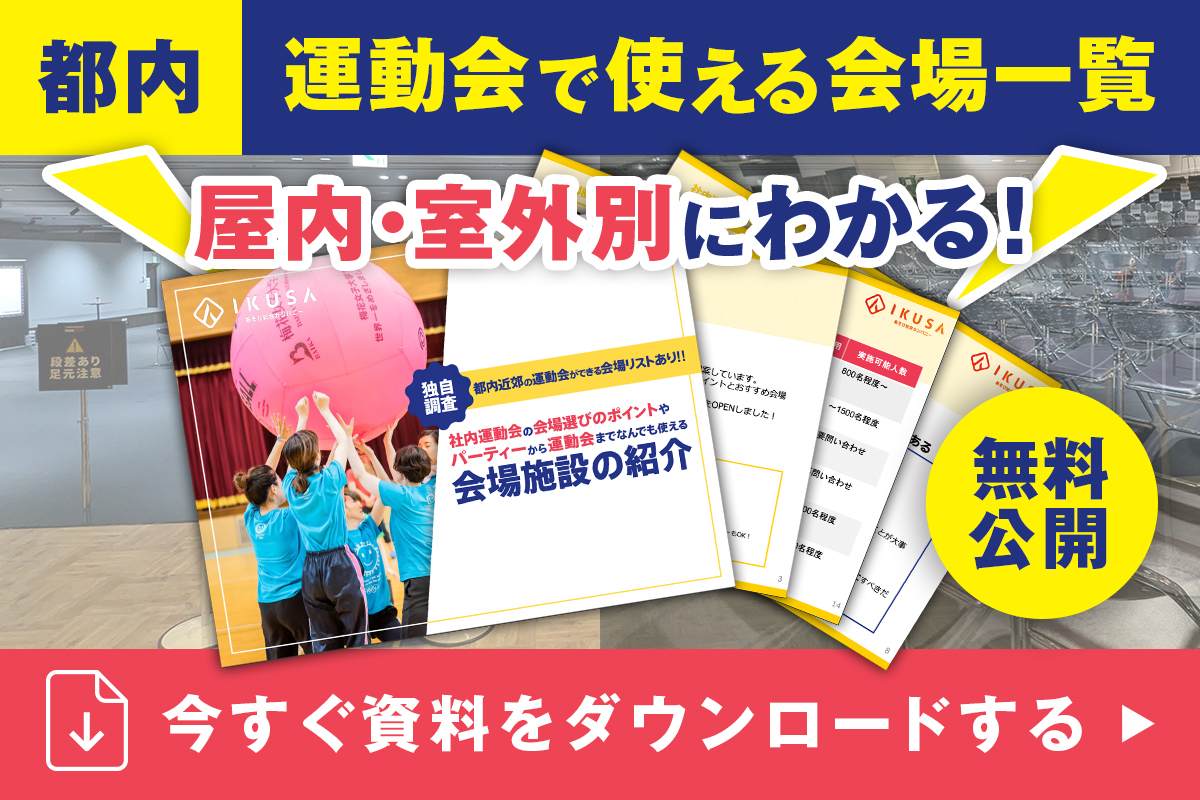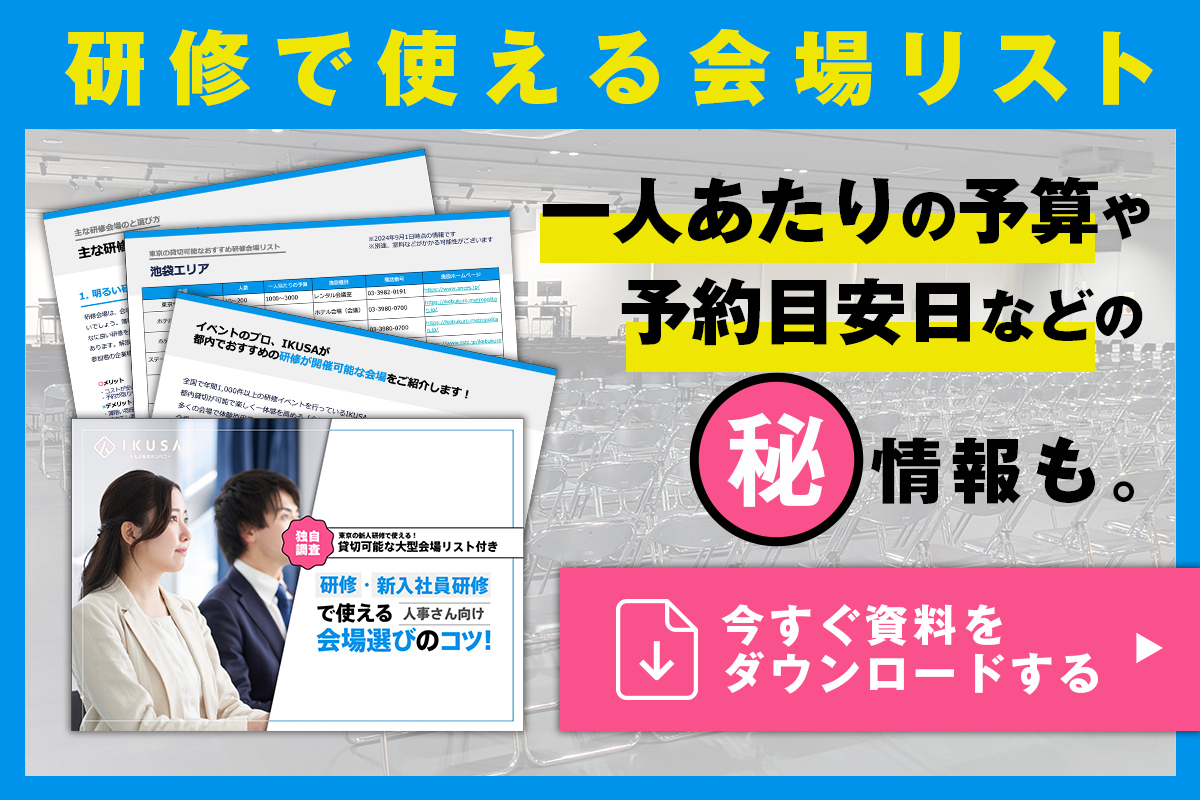パブリックビューイングとは?実施するメリットや企画のポイント・企画手順・開催事例を紹介

目次
パブリックビューイングは、スポーツの試合や音楽ライブなどを多くの人と一緒に楽しむ企画です。遠く離れた場所からでも臨場感溢れる映像を大画面で共有できるため、地域のイベントや店舗の集客にも適しています。ただし、開催には著作権などの法律面での注意点も多く、しっかり準備を進めることが成功の鍵となります。
本記事では、パブリックビューイングの基本から実施するメリット、企画のポイント、企画手順、実際の開催事例を紹介します。
大人数のレクリエーションにぴったりの会場をお探しですか?都内有数の広さと充実した設備を持つ「IKUSA ARENA」なら、企画・運営まで一貫してサポートできます。
パブリックビューイングとは

パブリックビューイングとは、大型スクリーンやモニターを用いて、映像コンテンツを観客と共有しながら楽しむイベント形式のことを指します。スポーツの試合や音楽ライブ、映画、花火大会、式典など、放映される内容は多岐にわたり、エンタメ性の高いものから記念行事までさまざまです。特にリアル会場での開催では、観客同士がその場の空気や熱気を共有でき、臨場感溢れる体験を提供できるのが魅力です。
また、近年ではオンライン配信形式のパブリックビューイングも増えており、物理的な距離にとらわれず、多くの人が同時に楽しめる点でも注目されています。会場の規模や形式は、ホールや映画館といった本格的な施設から、バーやレストラン、公園などのカジュアルなロケーションまで、目的やターゲットに応じて柔軟に選べます。
パブリックビューイングを実施するメリット

パブリックビューイングを企画するメリットは、「観客に非日常的な体験を提供できること」です。会場の一体感や臨場感を共有できるため、イベントへの参加価値が高まり、来場者の満足度も上がる傾向にあります。加えて、主催者側にとっても、企業やブランドの認知拡大、ファンコミュニティの形成、リピーター獲得など、さまざまな波及効果が見込めるのもメリットです。
特に、メインイベントの補完的な位置づけで行うことで、会場に入りきらない観客への対応策となったり遠方からでも参加可能な形を整えたりと、柔軟な活用ができます。結果として主催者・参加者双方にとってメリットのあるイベント形態といえるでしょう。
パブリックビューイングを企画する前に確認すべきポイント

パブリックビューイングを企画する際には、視聴コンテンツに関する著作権やライセンスの扱いについて、十分な理解と準備が必要です。ここでは、パブリックビューイングの企画前に確認すべきポイントを紹介します。
営利目的か非営利目的か
イベントの開催意図によって、必要となる手続きやライセンスの取得方法が異なります。仲間内でのホームパーティーなど、プライベートな範囲での視聴は「非営利目的」にあたり、著作権の手続きは基本的に不要です。しかし、不特定多数を対象とする公開イベントの場合は、営利・非営利に関わらず、映像の利用に関するルールをしっかりと確認する必要があります。
映像・作品のライセンス申請は必要か
放映したい映像コンテンツに対しては、放送事業者や権利保有団体へのライセンス申請が必要です。特に大型スクリーンやプロジェクターを使って公開する場合、著作権法100条に基づく許諾(上映権や公衆送信権など該当する権利者からの許諾)が求められます。
例えば、NHKでは大型ディスプレイを使ったライブ放送には申請手続きが必要であると明記しており、違反した場合は法的な問題につながる恐れがあります。家庭用テレビを使用して、特定の利用者に限定して視聴する場合は、許諾が不要なケースもあります。
なお、各放送局の許諾手続きは随時変更される可能性がありますので、最新の情報は公式サイト等でご確認ください。
著作権侵害に該当しないか
個人が購入したDVDや市販の映像作品をスクリーンで放映する場合は、個人使用の範囲を超えてしまい、著作権侵害にあたる可能性があります。上映を企画する際は、著作権処理が済んだメディアを使用することが求められます。
また、YouTubeなどの動画投稿サイトに掲載された動画についても、非営利であっても不特定多数に公開する形で放映することは禁止されています。事前に使用許諾やガイドラインを確認し、安心してイベントを実施できるようにしましょう。
なお、YouTubeなどの動画投稿サイトに掲載された動画についても、非営利であっても不特定多数に公開する形で放映することは禁止されています。加えて、アップロード者が必ずしも権利者でない場合が多いため、公式に許可されたコンテンツを除き、無断使用は避けたほうがいいでしょう。事前に使用許諾やガイドラインを確認し、安心してイベントを実施できるようにしましょう。
パブリックビューイングの企画方法

パブリックビューイングを成功させるには、企画から当日運営、そして振り返りまでを一貫して丁寧に進めることが重要です。ここでは、実際の運営ステップを具体的に紹介します。
1.目的と放映する内容を決める
まずはパブリックビューイングの目的を明確にしましょう。例えば、地域のお祭りやフェスの一環として多くの人が集まる機会を作りたいのか、スポーツや格闘技の試合をリアルタイムで多くの人に見てもらいたいのか、飲食店の集客イベントとして企画したいのかで準備の方向性が変わります。目的に応じて放映する映像の種類や内容を具体的に決定することで、企画のコンセプトがぶれず、参加者のニーズにも応えやすくなります。
また、学校や会社の式典をオンライン配信し、来場できない人にも視聴の機会を提供するなど、企画の規模やターゲットも明確にしましょう。目的の設定は関係者間の共通認識を持つうえでも重要なステップです。
2.使用ライセンスの申請をする
パブリックビューイングで映像を放映する際は、映像の著作権を管理している団体や権利者から正式なライセンスを取得する必要があります。これは法律で定められているため、無断での放映は法的トラブルに発展する恐れがあるので注意が必要です。
スポーツ試合の放映権、音楽ライブの配信権、映画や番組の上映権など、それぞれに異なる権利関係があるため、事前に権利元と詳細を確認し、申請手続きを進めます。申請には時間がかかることもあります。企画が固まった段階で速やかに対応することがトラブル回避につながるでしょう。
権利者との契約条件や使用範囲を正確に把握し、違反がないよう慎重に準備しましょう。
3.日程と開催場所を決める
パブリックビューイングは、放映するイベントの日時と連動して開催日を決めるのが基本です。スポーツの試合やライブ配信など、リアルタイム性が重要な場合は特に日程の調整が大切です。
開催場所は参加人数や企画内容に応じて選びます。イベントホールやレンタルスペース、飲食店やホテルのロビー、広場や公園、さらにはオンライン開催も選択肢となるでしょう。また、会場の設備状況やアクセスのよさ、駐車場の有無なども考慮しましょう。屋外で開催する場合は天候リスクも考え、雨天時の対応策も用意しておくと安心です。
参加者が快適に視聴できる環境を整えるために、複数会場の検討や機材配置計画も念入りに行うことが成功のポイントです。
4.必要な機材を揃える
パブリックビューイングで重要なのは、映像と音響の質です。大型LEDビジョンやプロジェクター、スクリーンは映像の迫力を左右します。また、音響設備も音のクリアさや会場全体への音の届き方を確認して選びましょう。
インターネット環境やパソコンの性能もライブ配信には不可欠です。会場が広ければ複数の小型ディスプレイを設置して視認性を高めたり、観客席の配置を工夫したりすることも効果的です。
機材は会場の特性に合わせて選び、事前に動作確認や設置のリハーサルを行うことでトラブルを防止できます。専門業者に依頼する場合も、要望を具体的に伝え、適切な機材手配を心がけましょう。
5.告知・集客する
パブリックビューイングの集客には多様な告知方法を組み合わせるのが効果的です。自社のホームページやSNSを活用するほか、ファンクラブや会員限定ページ、地域のイベント情報サイトなども活用しましょう。WEB広告やSNS広告はターゲット層にダイレクトにリーチできるため効率的です。紙媒体のチラシやポスターも地域密着型の集客には有効です。
告知時には開催日時や場所、参加費や支払い方法、事前申し込みの有無などの情報を分かりやすく記載し、参加者が迷わないようにしましょう。参加数を正確に把握するためにWEB上での事前申し込みフォームを設置し、集客状況をリアルタイムで管理することもおすすめです。
6.運営の準備を進める
イベント当日の運営体制を整えることは、スムーズな進行のために不可欠です。スタッフの役割分担を明確にし、機材担当や受付担当、案内係などを決めておきましょう。特に映像や音響機材の操作には専門知識が必要なため、経験者を優先的に配置することが望ましいでしょう。
機材トラブルや来場者のトラブル発生時の対応方法を事前にスタッフ間で共有し、マニュアルやチェックリストを準備しておくことで、当日の混乱を防げます。また、スケジュールや役割分担は一覧表にまとめて共有し、全員が状況を把握できる体制を作りましょう。
7.会場設営・リハーサルを行う
本番前には会場設営を完了させ、映像や音響の最終チェックを行いましょう。ディスプレイの設置場所や角度、音の聞こえ方を実際の来場者の視点で確認することが大切です。受付や観客席の導線、スタッフの動線もリハーサルを通じて問題点を洗い出し、混雑やトラブルを回避できるよう準備します。
映像の出力テストやネットワーク環境の安定確認も欠かせません。リハーサルはスタッフ全員が参加し、当日の流れを共有するとともに役割の確認や緊急時の対応も練習しておくことで、より安心して本番に臨めます。
8.イベント当日
当日は事前に決めたスケジュールに沿ってイベントを進行します。スタッフ間は無線機やインカムで常に連絡を取り合い、急なトラブルや変更にも迅速に対応できるようにしましょう。
来場者の安全管理や快適な視聴環境の確保にも細心の注意を払い、質問や要望には適切に対応することが大切です。イベント中は映像や音響の状態をこまめにチェックし、問題があればすぐに対処する体制を整えておくことで、参加者の満足度向上につながります。
9.振り返りを行う
イベント終了後は参加者アンケートやスタッフのフィードバックを収集し、よかった点や改善すべき課題を整理します。これにより次回開催時の品質向上や運営効率化が図れます。
アンケートでは参加者の満足度だけでなく、集客方法や会場設備、運営体制についても意見を聞くことが重要です。また、参加者への感謝のメッセージとともに次回開催の案内や特典を提供することで、リピーターの獲得にもつながります。こうした振り返りを丁寧に行うことが、継続的な成功の秘訣です。
パブリックビューイングの開催事例

実際の開催事例を通して、パブリックビューイングの魅力や工夫を具体的に紹介します。参加者が一体感を感じられる空間作りや、多様な企画のヒントになるでしょう。
特設会場でサッカー日本代表戦のパブリックビューイング
サッカー日本代表の試合に合わせて、複数の会場でパブリックビューイングが開催されました。メイン会場では元プロサッカー選手を招き、試合前のトークショーを実施し、参加者の盛り上がりを演出しました。
会場内には複数の大型ディスプレイが設置され、来場者は人工芝の上に座って快適に試合観戦ができる仕様です。さらに、歴代日本代表チームのユニフォーム展示や、選手へ向けた応援メッセージカードの配布など、ファンが楽しめる特別企画も展開されました。試合の臨場感だけでなく、参加者同士の一体感も高める工夫がなされたパブリックビューイングです。
参考:3面特大スクリーンのGINZA456で「新しい景色を2022 つながる!パブリックビューイング」開催|KYODO NEWS PRWIRE
地域密着型イベントとしてのパブリックビューイング
滋賀県のプロバスケットボールチーム「レイクスターズ」が開催したパブリックビューイングは、地域のファンを対象に特設会場で実施されました。
試合のライブ中継に加え、選手との交流会やサイン会、グッズ販売など、参加者が楽しめるコンテンツを多数用意し、ファミリー層や若年層にも配慮したイベント設計で、幅広い層から支持を集めました。
また、地元メディアやSNSを活用した告知で集客力を高め、地域コミュニティの活性化にも貢献しています。こうした多角的なアプローチは、パブリックビューイングを成功させるためのポイントの1つといえるでしょう。
参考:【レイクスとのすてきな関係】vol.3 三井アウトレットパーク滋賀竜王|SHIGA LAKES
eスポーツイベントにおけるパブリックビューイング
東京都を拠点とするeスポーツチーム「ヴェルカ」は、大規模なeスポーツ大会の開催にあわせてパブリックビューイングを企画しました。
会場には高解像度の大型スクリーンと最新の音響設備を整え、選手のプレイをリアルタイムで迫力ある映像と音で楽しめる環境を提供しました。また、来場者が交流できるスペースも設け、ファン同士のコミュニケーションを促進しました。
加えて、イベント限定のグッズ販売や参加型のミニトーナメントも実施され、来場者の満足度向上に成功しています。デジタルコンテンツとリアルイベントの融合を実現した先進的な開催例です。
参考:出島メッセ×V・ファーレン長崎×長崎ヴェルカ共催「V・SPORTSDAY」開催のお知らせ|NAGASAKI VELCA
大型イベントで盛り上がったサントリーのパブリックビューイング
サントリーは大型スポーツイベントに合わせて、複数の都市でパブリックビューイングを開催しました。会場には大型スクリーンや高性能音響設備が設置され、多くのファンが集まりました。
飲料メーカーとしての特性を活かし、会場内でのドリンク提供やオリジナルグッズ配布も実施しました。参加者同士の交流を促進し、イベントの一体感を高める工夫がなされたパブリックビューイングです。
天候に左右されない屋内施設を活用したことで、快適な環境を提供でき、地域のファン層拡大にも貢献しています。
パブリックビューイングの開催には「IKUSA ARENA」がおすすめ!
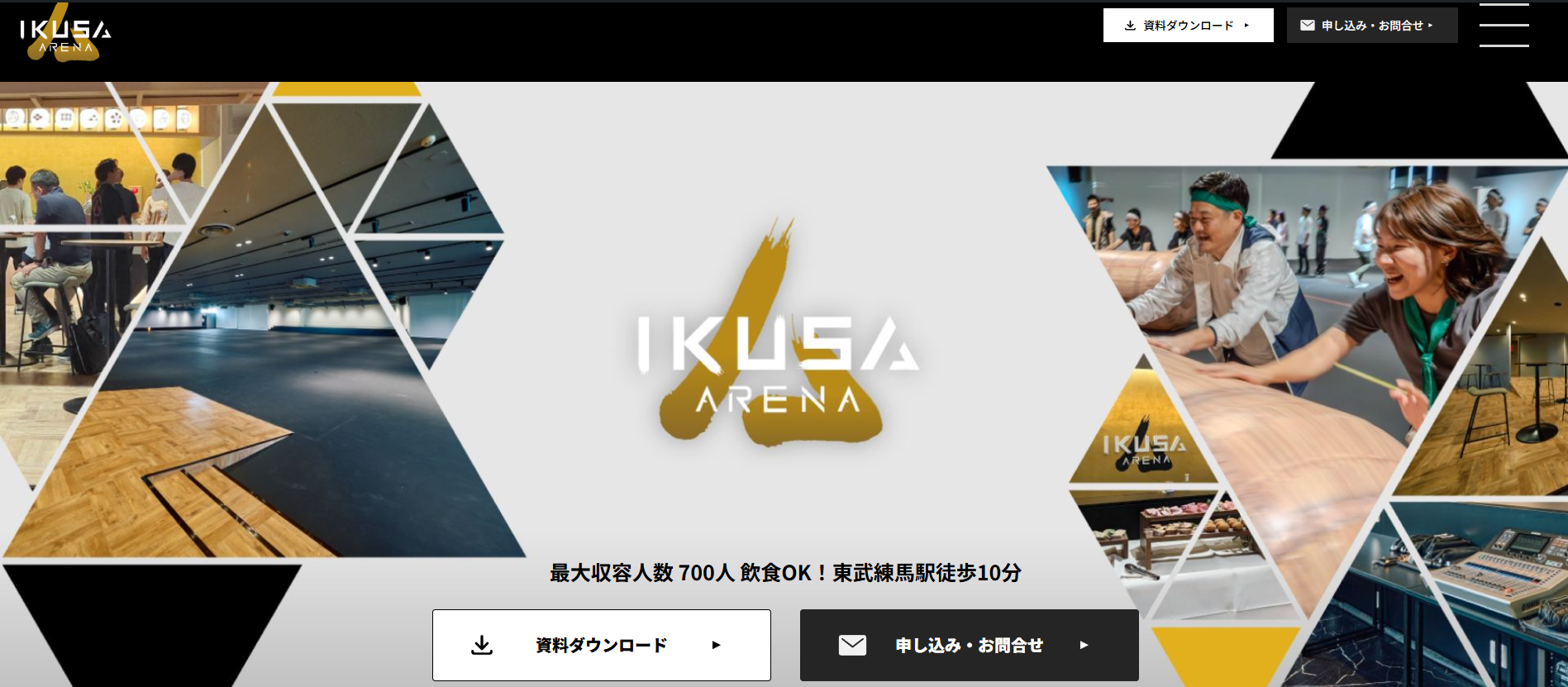
パブリックビューイングの開催には、大型スクリーンをはじめ映像配信機材、音響・照明設備、そして観客を収容できる十分なスペースが必要です。オンライン配信を行う場合は、安定したインターネット環境も欠かせません。
IKUSA ARENAは700名以上を収容できるアクティビティスペースを備え、映像や配信、音響、照明の各種機材が完備されています。室内施設なので天候に左右されず、快適な環境でイベントを開催可能です。
また、最寄駅からのアクセスも良好で、施設内で飲食ができる点も来場者に好評です。これらの特徴から、パブリックビューイングの会場として非常におすすめできる場所といえるでしょう。
まとめ

近年、スポーツ試合や音楽ライブ、企業や学校の式典など、さまざまなシーンでパブリックビューイングが活用されています。しかし、営利・非営利を問わず、放映映像には必ず著作権が存在し、権利元からのライセンス申請が必要です。無断放映は著作権侵害につながるため、トラブル防止のためにも企画段階から手順を踏んで適切に準備を進めましょう。
都内でイベント会場をお探しなら、700人まで収容可能なIKUSA ARENAがおすすめです。
スポーツイベントから懇親会まで、幅広い用途に対応できる会場の空き状況と料金プランを今すぐチェックしませんか?