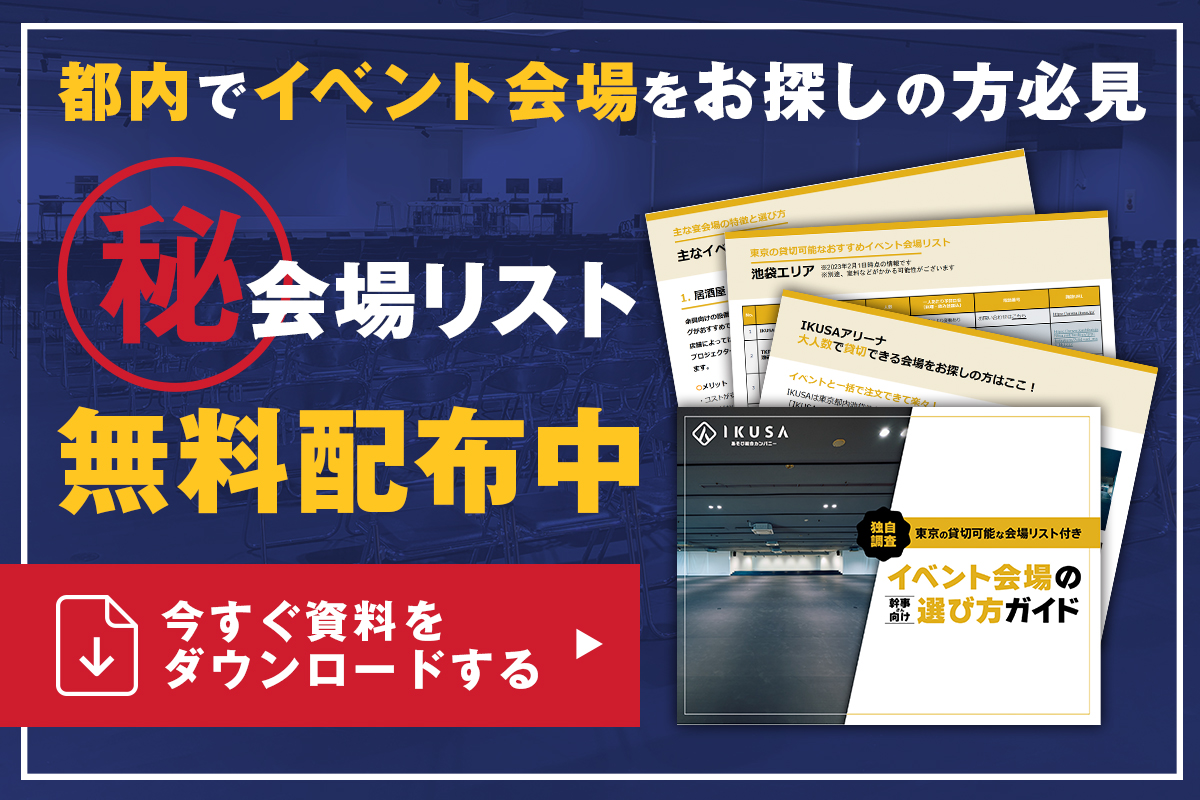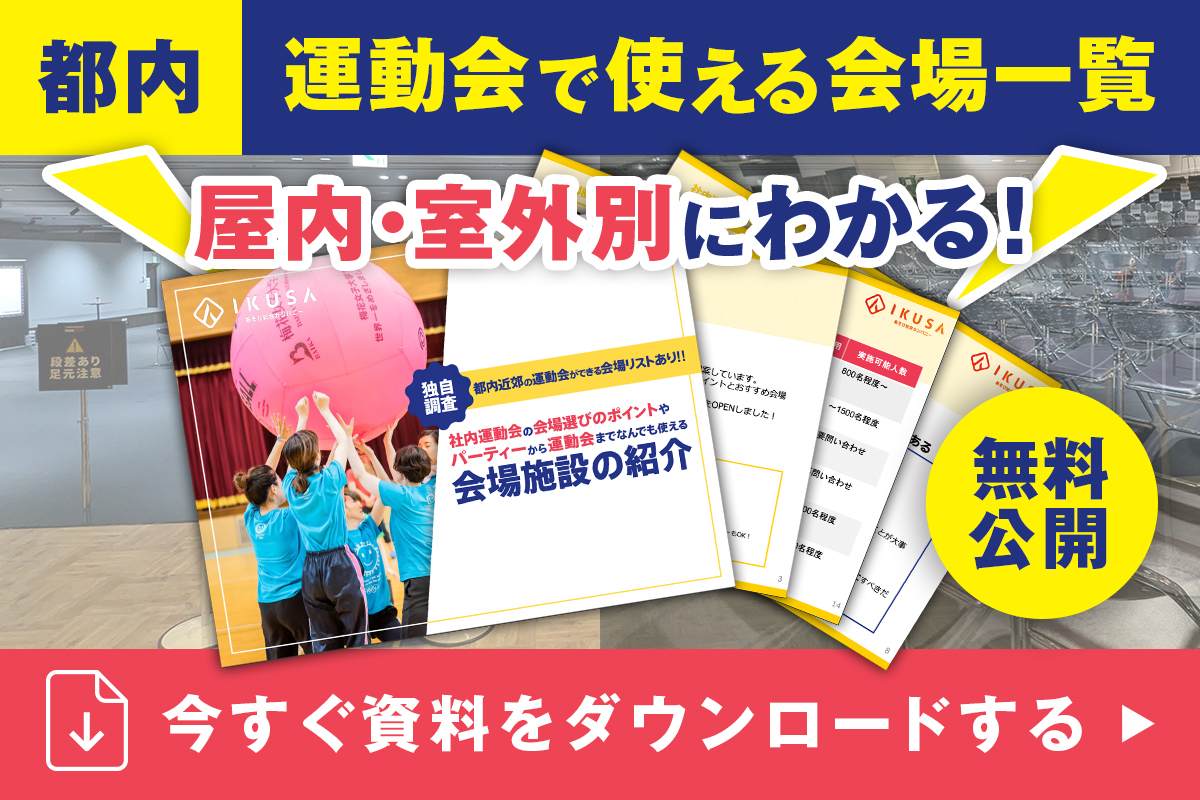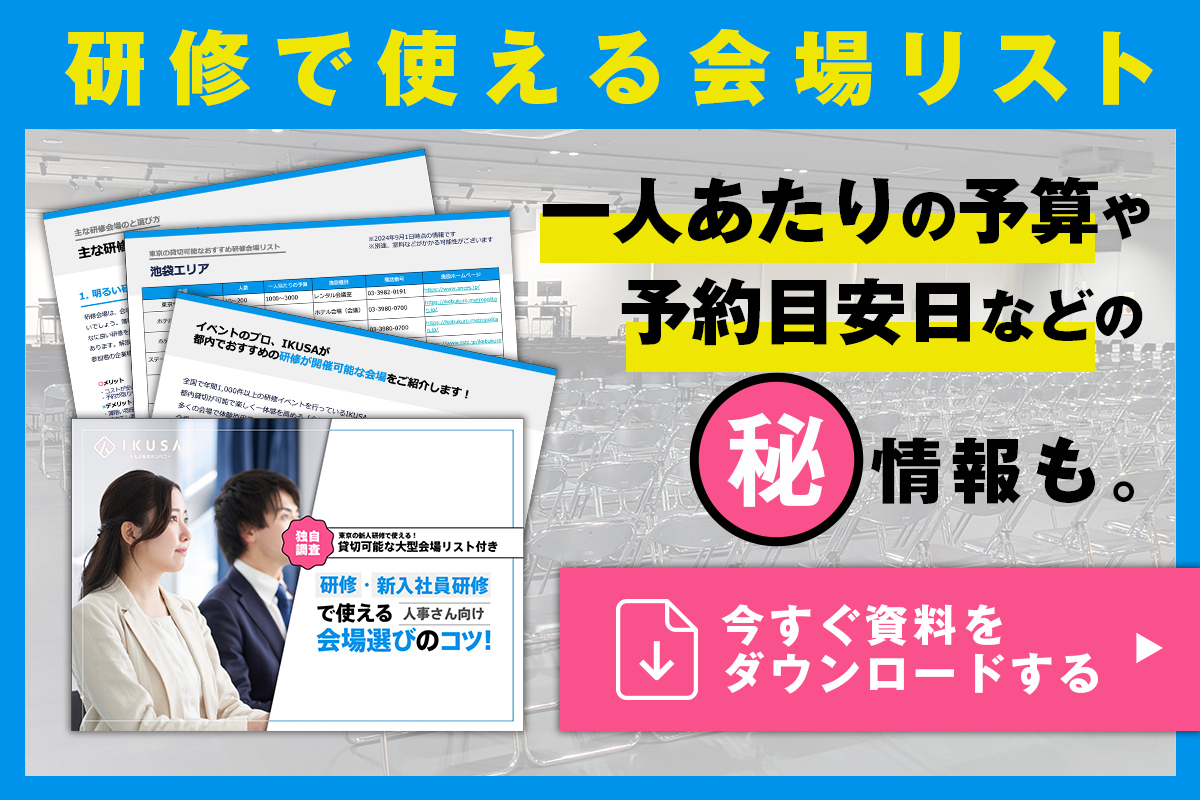ウェビナー運営を成功させる4ステップ|準備からアフターフォローまで解説

目次
ウェビナーとはオンラインで実施するセミナーのことで、近年はオフラインのセミナーからウェビナーへ移行している企業も存在します。しかし、初めての方にとっては、事前準備や当日の運営に不安を感じることも少なくありません。
本記事では、ウェビナー運営を成功させるために注意すべきポイントを解説します。
大人数のレクリエーションにぴったりの会場をお探しですか?都内有数の広さと充実した設備を持つ「IKUSA ARENA」なら、企画・運営まで一貫してサポートできます。
ウェビナーとは

ウェビナーとは「Webセミナー」の略称で、オンライン上で開催されるセミナーのことです。
オフラインのセミナーでは会場の確保に加え、受付や設営、備品手配など多くの手間が発生します。一方、ウェビナーなら撮影機材さえあれば大規模な会場は不要で、主催者にとって手軽です。さらに遠方の参加者も気軽に参加できます。
また、リアルタイムで配信する「ライブ配信」だけでなく、録画を活用した「オンデマンド配信」も可能です。リアルタイム配信を録画して後日配信することや、オフラインセミナーを撮影して配信するなど、ハイブリッド形式も普及しており、参加者のニーズに柔軟に対応できる点は大きな魅力です。
近年はリモートワークやDXの推進により、ウェビナーは営業・採用・教育研修など幅広い場面で活用されるようになっています。移動や会場費の負担を減らしつつ、多くの人に効率よく情報を届けられる点が評価されています。
ウェビナーの配信方式別のメリット・デメリット
ウェビナーの配信方式別のメリット・デメリットを以下にまとめました。
配信方式 | メリット | デメリット |
ライブ配信 | リアルタイムで配信できるため、参加者に没入感のある体験を提供できる | 通信環境や機材などのトラブルで配信が止まってしまうリスクがある |
録画配信 | 場所や時間を問わずに視聴できるため、視聴回数を増やせる | チャットやアンケートなどリアルタイムでのやり取りができないため、参加者の理解度が低下する可能性がある |
ハイブリッド配信 | 参加者のニーズに柔軟に対応できる | ライブ配信と録画配信、両方の工数やコストがかかる |
ウェビナーを主催する際は、メリットだけでなくデメリットも踏まえて配信方式を検討しましょう。
ウェビナー運営ステップ1:企画立案

ウェビナー運営を成功させるには、まずしっかりと企画を立てることが大切です。目的やターゲット層を明確にしたうえで内容や配信方法などを検討し、多くの参加者にとって有益なウェビナーを設計しましょう。
目的を明確にする
まずはウェビナーの目的を明確にし、ゴールを設計します。目的があいまいだとウェビナーの方向性が定まらず、時間やコストをかけても成果が出にくくなります。
ウェビナーの目的は、自社の認知度拡大や新規リードの獲得、既存顧客へのアップセル・クロスセルなどさまざまです。目的によってターゲット層や内容が変わってくるため、最初に明確に設定しておきましょう。
ターゲット層を設定する
次は、ウェビナーの目的に沿ってターゲット層を定めます。成果を出すには、ターゲット層に響く内容を企画することが欠かせません。そのため、ターゲット層が抱える課題やニーズを洗い出しておくことが重要です。
たとえば「自社の認知度拡大」が目的なら、ターゲット層は「まだ自社を認知していない人」となります。業種・職種・役職・年代といった部分まで具体的に人物像を設定すると、ターゲット層の課題やニーズをより深掘りできるでしょう。
KPI(成果指標)を設定する
ウェビナーの目的とターゲット層が明確になったら、次に「どのような状態を成功と定義するか=KPI(重要業績評価指標)」を設定しましょう。KPIは後から振り返るための指標となるだけでなく、企画段階で設定しておくことで、ターゲットへの訴求方法や告知内容、進行スタイルまで一貫性を持たせることができます。
ウェビナーでは、以下のようなKPIが代表的です。
- 新規リードの獲得が目的 :「申込数」「参加率」「資料請求数」
- 既存顧客との関係構築が目的 :「平均視聴時間」「アンケート回収率」
- サービス導入への動機づけが目的 :「ウェビナー後の問い合わせ件数」「商談化率」
KPIは1〜2点に絞ると構成や評価がシンプルになり、次回以降の改善にもつながります。「なんとなく開催して終わり」にならないよう、ゴールを見据えたKPI設計が重要です。
内容を企画する
ここまで決めてきた項目を基に、ウェビナーの内容を企画します。ターゲット層の抱えるニーズや課題に合わせて、有益な情報を届けられるテーマにしましょう。
たとえば、ゴールが「商品やサービスの紹介」というウェビナーでも、「新商品の紹介」といった直接的なテーマだと営業色が強くなり集客効果が薄れるリスクがあります。一方で、「在宅勤務でよくある課題とその解決策」や「生産性を高めるための新しい働き方」といった参加者の悩みに寄り添うテーマであれば、自然に自社サービスを紹介する流れにつなげられるでしょう。
また、他社と同じようなテーマでは埋もれてしまうため、差別化を図ることもポイントです。たとえば、実務経験者や現場責任者によるリアルトーク、事前に参加者の悩みを集めて当日解決するスタイル、後日PDFや動画などプラス特典配布を前提にした設計などがおすすめです。
配信方法やツールを選定する
ライブ配信、録画配信、ハイブリッド配信のいずれにするかを決めましょう。それぞれのメリット・デメリットを比較検討することが大切です。
ライブ配信の場合は、使用するツールも選定する必要があります。ウェビナー専用ツールにはチャットや画面共有、アンケート機能などが備わっており、参加者とのコミュニケーションが取りやすいというメリットがあります。ウェビナーに活用できる主なツールを以下にまとめました。
ツール名 | 特徴 | 対応人数 | おすすめの用途 |
Zoom Webinars | Zoomと同じインターフェースのため使いやすい | ウェビナーライセンスによって異なる | 大規模ウェビナー |
V-CUBEセミナー | ウェビナーの準備から本番までのサポートサービスがある | 最大26,000人 | 小規模~大規模ウェビナー |
Adobe Connect | Adobe製品との接続ができる | 最大1,500人 | 小規模~中規模ウェビナー |
目的や規模に応じて、使い分けるとよいでしょう。
ウェビナー運営ステップ2:準備

準備をどれだけ丁寧に行えるかが、ウェビナー運営の成否を分けます。ここでは、集客や会場選び、機材の用意など、実施前に押さえておくべき準備のポイントを解説します。
集客する
準備段階で重要なのが集客です。ライブ配信をする場合は集客が必要となるため、集客するチャネルを決めて告知しましょう。集客方法としては、自社のWebサイトでの告知が一般的です。Webサイトにウェビナーの情報を掲載したページを作り、申込みフォームを設置しておきましょう。
また、自社のWebサイトだけでなく、SNSやメールも活用すると集客効果が高まります。ターゲット層に合わせた主な集客方法は、以下の通りです。
- 新規顧客向け:Web広告やSNS、告知サイト、プレスリリース
- 既存顧客向け:メルマガやDM
- BtoB向け:プレスリリースや業界メディア掲載
申込み後に忘れられると参加率が下がるため、ウェビナー開催日の1週間前・1日前・1時間前などにリマインドメールを配信しましょう。
新規顧客を対象にする場合は、告知時に「参加者限定の資料プレゼント」や「次回無料トライアル」などの特典を用意すると効果的です。また、SNSでは告知だけでなく当日の様子をライブで発信することで、次回以降の参加意欲を高める効果も期待できます。
撮影場所を決める
ウェビナーはオンライン開催のため大規模な会場は不要ですが、配信場所はあらかじめ決めておく必要があります。オフィスで配信する場合、雑音や映り込みで参加者の集中力が途切れたり、会話が入って情報が漏れたりするリスクもあります。そのため、以下のような場所が候補となるでしょう。
- 社内会議室:小規模ウェビナーでコストを抑えたい場合におすすめ
- 貸し会議室やレンタルスペース:静かで清潔な環境を確保でき、安心感を与えられる
- 配信スタジオ:音響や照明が整っており、高品質な映像や音声が求められる大規模配信にぴったり
撮影機材を用意する
撮影に必要なカメラやマイク、配信用のパソコンなど、配信機材を用意しましょう。内蔵カメラやマイクだけでは品質が低く、参加者にストレスを与える恐れがあります。参加者の離脱につながるリスクもあるため、性能の高い配信機材を用意しておきましょう。動画の質を高めるために、外付けの高性能マイクやミキサー、照明用のライト、業務用のビデオカメラなども準備しておくと安心です。
自社で新たに配信機材を用意する場合には購入費がかかるため、機材レンタルサービスの活用やプロ仕様の設備が整ったスタジオのレンタルも検討しましょう。
コンテンツを作成する
ウェビナーで使用するコンテンツは事前に準備しておきましょう。オフラインのセミナーでは配布資料が中心ですが、ウェビナーではスライドや映像といった視覚的なコンテンツが効果的です。スライドは図解やイラストを取り入れ、文字数を抑えてスマートフォンからでも見やすい構成にしましょう。
映像を用いる場合は、長すぎると参加者が飽きてしまうため、伝えたいポイントを絞り、短時間で理解できるようを心がけることが大切です。また、参加者の理解を深めるために補助資料を配布すると、ウェビナー後の学びや振り返りにもつながります。
リハーサルをする
ウェビナーを成功させるには、入念なリハーサルも重要です。オフラインのセミナーでは参加者の反応を直接把握できますが、ウェビナーは画面越しのため反応が見えにくいという課題があります。そのため、チャットやアンケートをどう活用するか、事前にリハーサルして確認しましょう。
また、リハーサルではスライドの見やすさや講師の話し方、身振り手振りなども確認します。画面越しで確認すると「動きが単調」「スライドが読みにくい」といった改善点が見つかることも少なくありません。事前に調整しておくことで、本番はスムーズに進行できます。
ウェビナー運営ステップ3:実施

万全に準備を整えたらいよいよ本番です。オンライン開催のウェビナーでは、機材トラブルが起きると参加者の信頼を失う可能性があります。インターネット回線やパソコンなどは本番直前までしっかりとチェックしておきましょう。ここでは、ウェビナー実施時に押さえておきたいポイントを紹介します。
ライブ配信でも録画する
リアルタイム配信の場合でも、忘れずに録画しておきましょう。録画データは見逃した人へのフォローだけでなく、後日のオンデマンド配信や営業・採用などへの二次利用もできます。録画しておけば「開催して終わり」だけでなく、継続的に成果を得られます。
双方向のコミュニケーションを心がける
ウェビナーは対面と違い、参加者の反応が見えにくいため、意識的に双方向のコミュニケーションを取り入れることが大切です。定期的に「ご質問はありますか」と声をかけたりチャットやアンケートを活用したりして、理解度を確認しましょう。
ほかにも「途中でクイズを出す」「視聴者投票によって話の展開を変える」「リアルタイムの抽選」「視聴者限定特典」などで参加者を巻き込みながら、飽きさせないような工夫を盛り込むのがおすすめです。こうした双方向の仕掛けを取り入れると、参加者は「自分ごと」として内容を捉えやすくなり、アンケート満足度や商談化率の向上にもつながります。
トラブルには迅速に対応する
当日は思いがけないトラブルが起こる可能性もゼロではありません。想定されるトラブルの事例と対応策をまとめました。
よくあるトラブル事例 | 対応策 |
当日「参加方法がわからない」という問い合わせがきた | l 事前に参加方法に関する案内をメールで送付しておく l 当日の問い合わせもすぐに返信できる体制を整える |
講師のインターネット環境が不安定で、音声や映像が乱れる | l 開催前にインターネット環境を確認しておく l 共同ホストを用意しパソコンを切り替えられるようにする |
特定の参加者が不快になるようなチャットを送っている | l 個別に注意する l 注意しても収まらない場合は、チャット機能を閉鎖したり強制退室させたりする |
誤って不要な画面を共有してしまった | l 不要なタブやウインドウは事前に閉じておく l 誤って共有したらすぐに謝罪して正しい画面を表示する l 情報漏えいがあった場合は迅速に対応する |
トラブルへの対応が遅れると参加者の離脱を招くリスクがあります。運営スタッフ間で役割を分担し、迅速に対応できる体制を整えておきましょう。
ウェビナー運営ステップ4:アフターフォロー
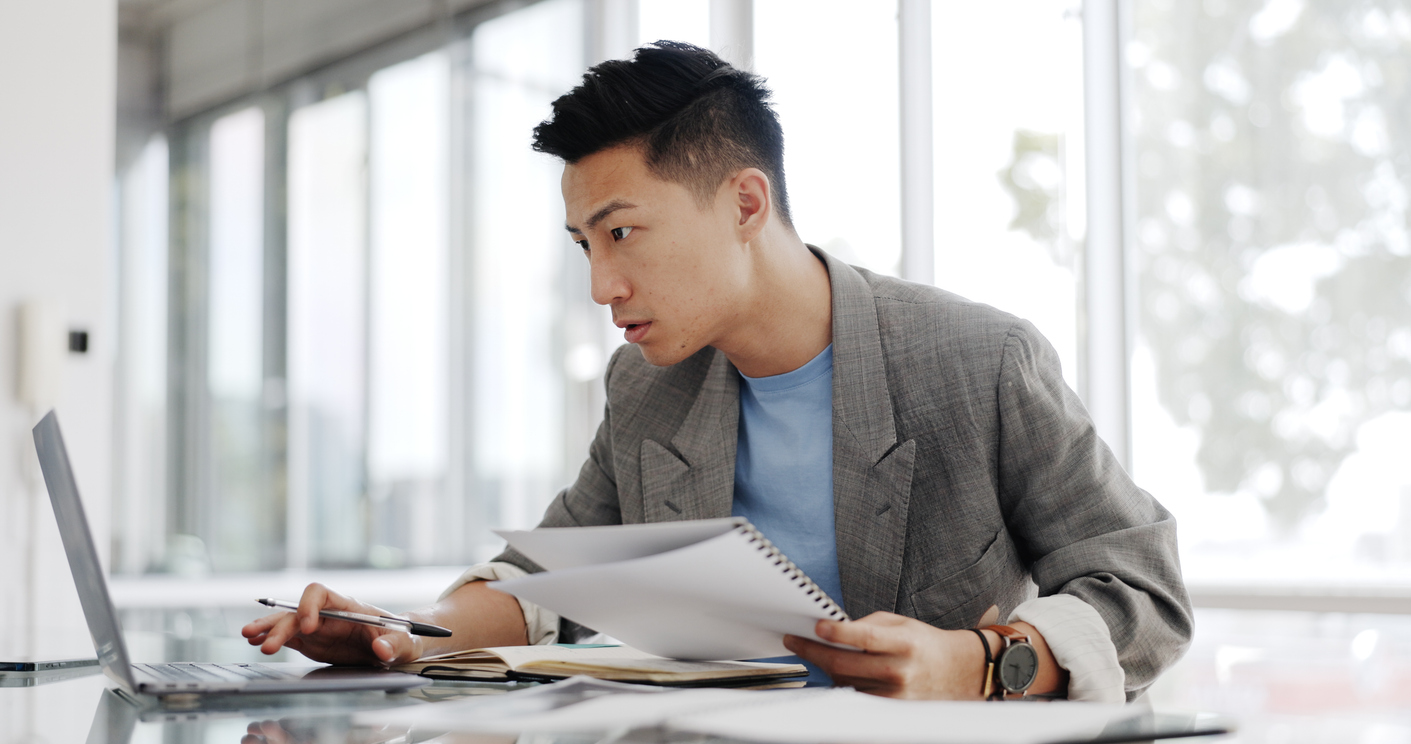
ウェビナーは配信して終わりではありません。アフターフォローを行うことで参加者との関係性を深め、次回以降の改善にもつなげられます。ここでは、実施後に取り組むべきポイントを紹介します。
ウェビナー参加者へアンケートを取る
参加者からアンケートを回収することで、内容に対する評価や改善点を把握できます。5段階評価や選択式など、回答しやすい形式にすると回収率が上がるでしょう。あわせて自由記述欄で要望を聞き取るのも効果的です。さらに、アンケートで氏名やメールアドレスを取得しておけば、その後のメール配信や営業活動にも活用できます。
視聴回数や問い合わせ件数などの効果測定を行う
ウェビナーはオンラインで行うため、参加者の行動をデータとして把握できる点が強みです。視聴回数や平均視聴時間、離脱率などのデータを分析し、参加者がどのタイミングで関心を持ったか・離れたかを確認しましょう。
また、ウェビナー経由での問い合わせ件数や購入件数など、ビジネスの成果につながったかどうかも測定が必要です。データを基に改善策を考えれば、次回はさらに効果的なウェビナーを運営できます。
アンケートや効果測定の結果は、社内で共有しナレッジとして蓄積しましょう。成功事例や改善点をチーム全体で把握することで、次回のウェビナーだけでなく営業活動や広報施策の質向上にも役立ちます
ウェビナー配信にはIKUSA ARENAがおすすめ!
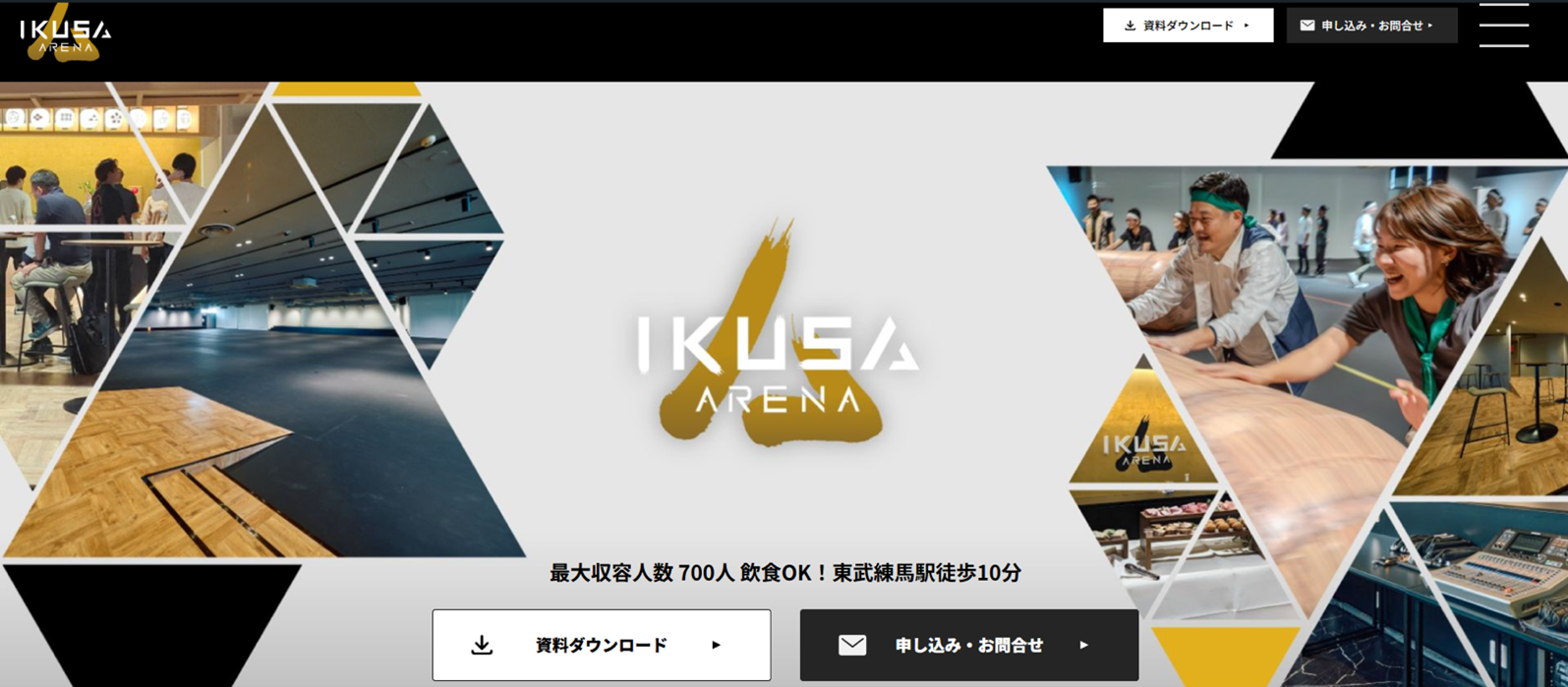
ウェビナーを成功させるには、静かで清潔な空間や安定したインターネット環境、そして十分な撮影機材が必要です。イベントスペースのIKUSA ARENAには、音響機材や照明設備が充実しており、ウェビナー会場としても活用できます。
130インチの大型スクリーンには大迫力の映像を映し出せるため、参加者の印象に残る配信が可能です。ウェビナー運営を検討している方は、ぜひ一度お問い合わせください。
まとめ

ウェビナーはオンラインで開催するセミナーのことで、時間や場所を問わず多くの参加者を集められる点が大きな魅力です。成功させるためには、目的やターゲットを明確にした企画立案から始まり、集客や会場・機材の準備、本番での円滑な進行、そして実施後のアフターフォローまで丁寧に行うことが欠かせません。
こうした一連の流れを意識することで、参加者の満足度を高められるだけでなく、リード獲得や顧客育成といった成果にもつながります。ウェビナー運営を成功させたい人は、今回紹介したポイントを参考に、次回の開催に役立ててください。
都内でイベント会場をお探しなら、700人まで収容可能なIKUSA ARENAがおすすめです。 スポーツイベントから懇親会まで、幅広い用途に対応できる会場の空き状況と料金プランを今すぐチェックしませんか?